 コピーライトの史的展開
(5)
コピーライトの史的展開
(5)

──成文法の制定とその影響──
白田 秀彰
|
評判の悪かった検閲制度との分離を果たすことで、コピーライトは、
独立の権利としての確立を模索することになる。
その過程で積極的な推進役をはたしたのは、またしても書籍業カンパニーだった。
「国王大権」も「国家の治安」という大義名分も使えなくなった彼らは、
1643年の請願と同じように「学問の振興」という題目を持ち出すことにした。
出版業の隆盛が学問の振興に貢献するという理屈である。 1704年のディフォーの小冊子が示したように、文筆家だけでなく、 政府内部でもコピーライトを「著作者の権利」として把握するようになっていたから、 この時期に著作者たちが団結して行動していたならば、 あるいは後世のコピーライトの発展を全く異なったものにしていたかもしれなかった。 しかし、コピーライトの母体だった書籍業カンパニーの影響力が、 制定法上のコピーライトの性格を決定することになったのである。 1709年制定法 [1]は、 その最初の保護期間が満了するまでの 20年間近く、ほとんど忘れ去られていた。 この期間、イギリスの出版業では寡占化が進み、 それと同時にコピーライトも寡占され、 制定法によって補強されたコピーライト制度は出版業の独占を支えることになる。 こうして、制定法の効力というよりも市場支配の力により、 ロンドンの書籍業界は安定期を迎えた。この状況において、書籍業者たちは、 制定法を軽んじ登記を懈怠した。一方~ 大法官府は、 制定法に基づかない根拠の曖昧な救済を与え続けたのである。
14 成立過程 庶民院に提出された請願の中で、学芸の振興という名目が付加されたものは、 1707年2月26日に現れた [2]。 その内容は次のようなものである。
本を執筆するために、学識のある人物は多大な時間と多額の費用を費す。そして、 権利の譲受人によって印刷させるために、かなりの額の報酬と引き換えに、 あるいは彼自身と彼の家族の利益のために一部分の権利を残して、 著作者は原稿を譲渡するのである。そしてまた、譲受人にしても、 そのような彼らの財産を当てにして、 彼らの死後残される妻や子供たちのための準備をしているのである。しかし、 近年そのような財産が、同じ書籍をイギリスで印刷している、 あるいは海外で印刷して輸入している他者によってひどく侵害されている。 このことが、社会に大変役に立つ執筆の仕事から人々を遠ざけ、 権利者たちに多大の損害を与えているのである.....この請願は、著作者の財産保護を理由にして、 取引上の財産権の安全を保護するように誘導しているが、請願書を提出した人物が、 13人の書籍業カンパニーの中心人物だったことから、 保護の対象として重視されているのが著作者ではなく「譲受人」「購入者」 であることがわかる。
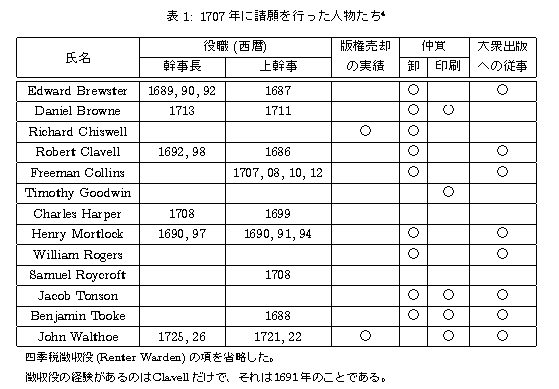
この請願に対応して、2月28日には草案がトファン(Richard Topham) 議員から提出されている。3月4日には、王立図書館、二大学、およびコットン図書館 (Cottonian Library) への納本が草案に盛りこまれ、さらにシオン(Sion) 大学への納本が追加された。この草案は、 3月18日に委員会の修正を受けて再び庶民院に送られたが、 審議が2週間延期されたまま、 立ち消えとなった [4]。 1709年12月には、1707年請願とほぼ同一内容の請願が、 16人の書籍販売業者から議会に提出されている [5]。これに応じて、 1710年1月11日に再び文学的財産(literary property) 保護のための草案が上程された。その草案は「学問を振興し、 正当な所有者の書籍の版についての財産権を保護するための法案 [6]」と題されており、 著作者についての言及はなかった [7]。 草案が上程されると、書籍業カンパニーの幹部は、特別の補佐役会を開催し、 「カンパニーのための条項を盛りこむ」ことが可決された。そして、 立て続けに請願が議会に提出されたのである。 記録として現存している請願書は4通あり、そのうち3通は印刷されたもので、 1通は議会記録に残されているものである。印刷された3通は、 ほぼ同じ内容のものである [8]。 第一の請願、「学問を振興するための法案について、 栄誉ある庶民院へ申し上げる書籍販売業者たちの請願 [9]」の内容は次のようなものである。 (1)この法案はコモン・ロー上の権利を承認するものである。(2)しかしながら、 コモン・ローは十分な保護を与えていない。(3) かつて1662年の制定法によってコモン・ロー上の権利が認められていたとき、 それによって、安価な書籍、適正な価格の書籍の出版が盛んだった。(4) 仮にこの法案が否決されたならば、書籍業界は崩壊するであろう。(5)書籍業界は、 検閲の廃止以来 長年にわたって不法行為に抵抗してきた。(6) 仮に印刷業界が崩壊したら、市民は利益を享受できないだろう。(7) この法案は出版の自由を制限するものではない。すなわち、 「[コピーライトの権利者] が希望しなければ彼の版を登記しないのだから、 何人も従属させられることにはならない。また、 著作者の許可がなければそのようなこと[登記]もできない。したがって、 出版所はこの法の下でもかつてと同じ程度に自由なのである。一方、 登記されていない書籍や小冊子はほとんどの場合 [保護に値するほどの収益が見込めないような種類のものであるから] 海賊出版の被害にあうこともない。」着目すべき点は、(7)の「この法律が出版の自由を制限しない」 と主張している点である。この主張が、 もはや検閲制度を復活させるつもりのなかったトーリー党穏健派とホイッグ党で構成 された議会の目を欺くための言い訳だったとしても、 検閲制度と自分たちの取引の安定の維持という目的が、 必然的に結合するものでないことに書籍業者たちは気がついたのである。 そして自分たちが享受している利益は「コモン・ロー上の権利である」 と主張しているのである。実際にコピーライトがコモン・ ロー上の権利であると認められたのは1774年のことであるが、 当時の社会を覆っていた既得権益を絶対視する雰囲気 [10]に強く訴える主張だった。 第二の請願、「学問を振興し、 正当な所有者たちの書籍の版についての財産権を保護する法案について、 栄誉ある庶民院へ加えて申し上げる論点 [11]」では、書籍業者たちは、 彼らのいう「コモン・ロー上の権利」を主張し、 前回の請願よりもややあからさまに自分たちの享受している利益を永久の財産権とし て承認するように求めている [12]。 第三の請願、「議会に提出された、書籍販売業者たちの版に関する権利、 またそれぞれの書籍の印刷に関する独占的権能の事例 [13]」では、 もはやこの請願が公の利益のためのものであるという粉飾を捨ててしまった。そして、 コモン・ローの下では、いかなる人物でも財産権を獲得すれば、 それが土地に対する権利であろうと、版に対する権利であろうと、 それを永久に享受することができる、と主張している。「今や自由は、 この古くから続く、そして合理的な慣習を根元から破壊しようとしている、 この慣習を効果的に維持するためには、 議会の制定法を除いて他に途がないのである [14]」 。 この請願に対応して作成された草案は、1710年2月2日に第二読会に付されて、 全院委員会に提出された。委員会で、いくつかの修正がなされた。 この委員会での修正をみるとき、 書籍業界の影響力がどのように働いたのかが見てとれる。 Whereas the liberty which Printers, Booksellers, and other Persons have of late frequently taken in [the Liberty of] Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted and Published Books, and other Writings, without the Consent of Authors thereof, in whom ye undoubted Property of such Books and Writing as the product of their learning and labour remains or of such persons to whom such Authors for good Considera^ons have lawfully transferred their Right and title therein is not only a real discouragement to learning in generll†which in all Civilized Nations ought to receive ye greatest Countenance and Encouragemt† but it is also a notorious lnvation of ye property of ye rightful [or] Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families:.....削除された部分を訳すならば、 彼らの学問と労働の成果として、 それら書籍と著述に存する疑いなき財産権が帰属する[著者]、またはそれら著作者が、 正当な報酬と引き換えに、そこに存する彼らの権利と権限を移転した者の同意なく [ 著述が勝手に出版されることは、] 全ての文明国家において一般的に多大な賛同と奨励を受けるべき学問の振興を真に阻 害するものであるだけでなく、正当な財産権への甚だしい侵害なのである.....削除された部分は、いずれも著作者の財産権について述べた部分であり、 著作者がコピーライトの保有者として存在し得ることをほのめかす部分が選ばれてい る。著作者が権利の全体あるいは一部分を保有することは、 書籍業界が注意深く独占を進めていたコピーライト取引の仕組みの中に、 著作者が介入することを意味する。このため、この条項は、 書籍業者たちには受け入れられないものだったのである。 以上のような委員会での修正を受けて、 2月25日に草案が庶民院に戻された [16]。庶民院では、 さらにスコットランドからの海賊版に罰金を科すための条項を盛りこむなどの修正が なされた [17]。 この庶民院の修正で、草案の表題は 「印刷された書籍の版の著作者または購入者にその版を帰属させることで学問の振興 をはかる法案[18]」 と変更された [19]。 この変更によって後に、権利が原始的に権利者に帰属しており、 法律はそれを保護する(securing)のか、あるいはこの法律によって付与される (vesting) のかが論争になる。しかし、いずれにしても、 この草案で初めて著作者が法律の考慮の中に入ったのである。この草案は3月14日に、 表題に「規定された期間に限り」(during the times therein menthioned) という文言が追加され、3月16日に貴族院に送られた。 貴族院では、3月16日に第一読会に付されたが、 次の審議は3月24日まで延期された [20]。3月24日に第二読会がなされ、 委員会に付託された。3月30日に全院委員会が開催され、 4月3日に 69人から構成される特別委員会で審議され、 翌日~以下の修正が加えられて庶民院に戻された。
1.について検討する。変更箇所を含む部分と対となる部分で、 1710年4月10日以後に出版される書籍の保護について言及していることから、 この部分は1709年制定法が施行される以前に出版された書籍の取り扱いについての規 定であり、 さらに変更箇所に続いて書籍業者たちが獲得した権利について規定していることから、 この変更箇所は、 すでに出版された書籍の著作者の権利について述べた部分であることは明らかである。 そこで、制定法となった1709年制定法の原文にあてはめると、草案のままならば、 版を売却して、もはや自分自身で版を保有していない著作者も保護されると読め、 一方、修正された表現であれば、 版を自分自身で保有している著作者のみが保護されると読める。 2月の委員会審議で削除された部分とつき合わせて考えれば、当初の案では、 1710年4月10日以前に著作者から出版者に譲渡された版についても、 何らかの保護を著作者に与えようとしていたが、 委員会によってその部分が趣意文から削除され、さらに残っていた 「著作者に残存していない」 版についても保護を与えるとする部分が委員会の削除に合わせて変更されたとするの が最もわかりやすい説明になるように思われる。
15 1709年制定法 1709年制定法は11条から成り、次のような構成になっている。
15.1 取引秩序維持1694年に印刷法が廃止されてから、ロンドンでは海賊版が横行し、 さまざまな誹謗文書が飛び交った。1709年制定法は、 書籍業カンパニーからの海賊版禁止の請願に対応して作られたものであるから、 当然に目的の一つは書籍取引秩序の維持だった。 これは同法1条と2条に規定されており、権利者の承諾なく出版することを禁止し、 出版前に登記を行うことを要求している。一時的に登記は検閲に必然の制度として利用され、 現在でも出版物の登記を検閲制度と結合して考える向きがある。しかし、 これまで見てきたように、登記制度は、 占有が不能なコピーライトを市場で取引する場合の権利者明認方法として自然発生し たものである。このことからわかるように、 コピーライトの権利関係を調整する前提として、登記制度は不可欠なものなのである。 誰が権利者であるかわからないときに、いかにして1条で要求されているように 「権利者の承諾」を得ることができるだろうか。 この登記簿の整備を前提に、権利保護の仕組みとして、 書籍業カンパニーが伝統的に行ってきた独占出版権の付与という手法を採用した。 著作者の保護と学問の振興だけを目的とするならば、 政府の補助金による手法もとりえたはずである。しかし、それをしなかったのは、 出版業界の取引秩序の安定に伴って著作者への経済的利益の還元が増大するという間 接的な回路で、「学問の振興」という目的が実現されると考えたからである。実際、 1709年制定法が施行されてから著作者への報酬額が増大したという [23]。また、 この手法の方が言論の自由を維持するという裏側の目的ともよく適合するのである。 登記制度が必要なものであるとしても、 書籍業カンパニーの登記簿を使用する必要はなかったかもしれない。というのは、 書籍業カンパニーの登記簿が古い歴史を持っているとはいっても、 その内容が不完全だったことはこれまで見てきたとおりだからである。それゆえ、 現在のアメリカのように著作権局を新設して、 そこで登記簿を一元管理するように規定してもかまわなかったはずである。しかし、 カンパニー側の強い要望で書籍業カンパニーの登記簿が使用されることになった。 これに対応して、書籍業カンパニーが登記事務から不当な利益を挙げたり、 恣意的な権力を揮えないように配慮がなされている。まず、 書籍業者のコピーライトでは、登記にカンパニーの監事の認証が必要だったが、 これは廃止され、 この法律の効果としてコピーライトが与えられることに変更されている。また、 2条後半で登記時に「6ペンスちょうどを支払うこと(Six Pence shall be Paid, and no more)」や、「費用や支払無しに(without any Fee or Reward)」 登記簿を閲覧できると規定するように、 カンパニーの事務員が登記費用6ペンス以上の金銭を要求しないよう、 あるいは登記者が賄賂を贈らないよう規定している。また、 3条でカンパニーの事務員が登記を懈怠した場合のカンパニーに依存しないコピーラ イトの獲得方法や、事務員への処罰規定が置かれている。 また立法者は、9条を置くことで、 書籍業カンパニーが確立してきた諸慣習を著しく破壊しないように配慮している。 9条は字句どおりに解釈すると理解困難な条文である。「前述の大学が保有する、 または保有すると主張する.... すでに印刷されてきた、 またはこれから印刷されるあらゆる版の印刷または再版に関する既得権を侵害しない ため、また権利を確認するために、 この法律のいかなる規定も拡大適用されない [24]」という部分は、 長年継続してきた印刷に関する大学の諸特権を維持する規定であると理解できるが、 大学と並んで既得権を認められる「あらゆる人物」(any Person or Persons) がどのような人物であるのかが明らかでない。書籍業者たちは、 いずれも多数の古典作品を印刷してきたし、またこれからも印刷するつもりだった。 さらに彼らはこれらの古典作品の出版権を主張してきたのだから、 この規定にも該当し得るわけである。しかし、この規定を書籍業者に適用するならば、 21年間の保護期間の規定が意味を失う。 この曖昧さのために、後のミラー 対 テイラー(Millar v. Taylor)事件で、 この条文が、著作者のコモン・ロー・ コピーライトを保護したものとして主張されるのであるが [25]、これは、 大学の既得権と並列して規定されていること、さらに文言の構造が、 1662年印刷法の18条および22条に規定されている大学の既得権への適用除外、 および国王勅許で既得権を持っている者への適用除外と類似していることから、 この条文も1662年印刷法18条、22条と同様に理解されるべきものである。したがって、 これは、 国王勅許によって認められてきた出版に関する諸特権をこの法律で排除するものでは ないことを規定したものなのである。 以上のように、 1709年制定法は書籍業カンパニーが作り上げてきた書籍取引秩序を確認する内容とな っている。
15.2 独占禁止これまで述べてきたように、 国王大権や書籍業カンパニーの営業統制力によるコピーライトの保護は、 独占の弊害を生み出してきた。したがって、1709年制定法のもう一つの目的は、出版市場における独占の排除だった。 1709年制定法以前では、国王勅許による場合を除き、 コピーライトによる保護を受けられるのは書籍業カンパニーの構成員に限られていた。 カンパニーの構成員以外は、登記することができなかったために、 多数の著作者が自分のコピーライトを出版者に売却せざる得なかった。しかし、 1条と2条を見ると、著作者が原始的に自分の版について独占出版権を保有する他に、 彼からコピーライトの譲渡を受けた人物ならば誰でも独占出版権を保有することがで きることになっている。 そして登記簿への登記をすることができる人物について何らの制限もない。そこで、 閉鎖的な「競り」 によってコピーライトが大手の書籍業者たちの内輪から外に漏れ出さないようにする ことができたとしても、1条と2条があるかぎり、 しだいに書籍業者たち以外にもコピーライト保有者が現れるのは避けようがない。 また、コピーライト保護に時間的制限を設けたことが注目される。 勅許による保護を除くと、書籍業者たちの間で、所有権と全く同一の「永久の権利」 として理解されてきたコピーライトに時間的制限が設けられたことは、 この法律での重大な変更である。コピーライト保護に時間的制限があるならば、 既存のコピーライトについて1732年以降、また、 1710年以降に出版された書籍についても1739年以降、 そのコピーライトを無断で使用した者を法によって処罰しないことになる。ただし、 保護期間満了後の権利の状態については、この法律では何も規定しなかったので、 この点が後に争いとなる。 議会側がカンパニーの独占を排除しようとしていたことを考えれば、これは コピーライトが永久に存続することを前提に構築された書籍業者による独占を廃止す るにあたっての執行猶予とみることができる。事実、 独占を廃止するために制定された1623年独占法の規定と 1709年制定法の規定は対応 しているのである。1709年制定法1条で規定された、 既存の版について21年間の独占出版権を与え、 また新たに創作された版について14年間の独占出版権を与えるという規定は、 1623年独占法の 5条で既存の特権について21年間の猶予を与え、 また6条で新規の発明に与える特許を14年間に限ったことと明らかな対応関係を持っ ている。後に法廷で主張されるように、「著作者に与える一般的特許」 としての性格をもっていたことは間違いない。 また、独占に付随する価格の高騰についても対策が設けられている。4条において、 全ての人に、 不当に高額に書籍を販売している業者を告発する権限を与えているのである。ただし、 この規定は、 議会と書籍業カンパニーとの取引で追加されたと思われる8条と10条で骨抜きにされ てしまっている。10条で訴追可能期間を3ヶ月に限り、 訴追される危険を減少させる一方、8条で、仮に原告敗訴の場合、 被告が原告に訴訟費用や損害賠償を請求し得るように規定することで、 ほとんどの場合、 原告が訴追にふみきらないように配慮されている [26]。このため、 4条は一度も使用されることがなかったのである [27]。
15.3 著作者の保護著作者とコピーライトを獲得した人物の享受する権利について検討してみるならば、 11条の「14年の保護期間の終了の後に、コピーライトが著作者に帰還し、 再び 14年間の保護を受けることができる」 という部分を除いて全く同一であることがわかる。成立過程をみるとわかるように、 1710年1月の草案まで議会は著作者の保護に重点を置こうとしていた。しかしながら、 法律では著作者が享受する権利を小さくする一方、著作者と同程度に、 版を獲得した権利者の保護に重点が置かれている。 これは書籍業カンパニーの議会工作の成果であるといえる。しかし、 著作者の権利を縮小することは、 書籍業カンパニーにとって必ずしも有利な点ばかりではない。この当時、 著作者から出版社へのコピーライト移転は、売買契約によって行われ、 著作者が保有する権利は完全に譲渡されていた。したがって1740年以降、 この制定法上のコピーライトの保護が期間の満了で消滅するときに、書籍業者たちが 「永久の権利である著作者の権利が自分たちに譲渡されているのだ」 と主張したことからもわかるように、著作者の権利を強化することは、 これを譲渡された書籍業者たちの権利を強化することにもつながったはずだからであ る。 また、仮に著作者がコピーライトを保有したとしても、先に述べたように、 出版業者たちは、閉鎖的なコピーライトの取引市場を形成することで、 実質的に著作者を締め出すことは不可能ではなかった。したがって、 書籍業者たちにとって、 著作者がコピーライトについて大きな権限を持つことを阻止する以上に重要なのは、 永久に存続する財産権としてコピーライトを法に盛りこむことだったはずである。 このように考えれば、 議会側がコピーライトの保護期間に時間的制限を設ける代わりの取引材料として、 著作者の権利を草案から削減したと考えることが自然である。 議会は著作者の権利を確立する以上にコピーライトに時間的制限を設けることを優先 したのである。 以上のことから見て、草案の段階で目的とされたのは次の三点であることがわかる。 優先順位で並べるならば (1)検閲を復活させず出版業界の取引秩序を確立する、(2) 大手書籍業者の市場独占力を排除する、(3)著作者の権利を拡張し学問を振興する、 ということになる。これが書籍業カンパニーとの交渉の過程で、(3) の目的が大きく後退した。すなわち、より重要な(1)(2) の目的を維持するために取引材料にされたのである。 パターソンは1709年制定法を「取引秩序維持のための法律であり、 書籍業カンパニーの独占を排除するための法律だった [28]」と結論している。 筆者もこれに賛成する。ただ、彼は(3)の目的を小さく評価しているが、 これまでたどってきた制定過程から判断する限り、議会側の意図としては(3) の目的も十分に視野にはいっていたのだと筆者は考える。しかし、(3)を譲歩しても (1)(2)の目的を優先させたという点で彼の主張は正当なものである。また、 パターソンは「この法律で与えられた保護は版の所有権から導かれたものではなく、 まして著作者の自然権から生じたものではない [29]」と主張する。 これまでのたどってきた歴史を見れば、1709年制定法で与えられた保護制度は、 1620年代に確立した書籍業カンパニーの慣習に基礎を置くものであることが明らかで あり、この点でも彼の主張に賛成する。
16 問題点
16.1 権利内容の曖昧さこれまでの論述でも訳語に迷った「版」(copy, copies) について、 この法律でも定義がなされなかった。この単語はあるときは「作品」を指し、 あるときはその作品に対する「権利」を指すのに用いられた。 出版者たちは著作者から原稿を買取っていたので、当然にそれは所有権(ownership) の目的物、すなわちコピーライトそのものであると理解していただろう。しかし、 この「版」が訴訟の目的として争われるようになる 1730年代以降には、 それがいかなるものかを改めて問いなおさなければならなくなっていた。また、権利者が「印刷の独占権および自由」(sole Right and Liberty of Printing) を一定期間保有すると規定されているものの、その期間が終了した後、 その権利が延長されない(and no longer)と規定する以外、「版」 がどのように扱われるのか、何ら規定しなかったのである。このため、 1709年制定法の保護期間についての規定は、二通りに解釈することができた。 コピーライトがこの法律によって与えられると考えるならば、 1710年以前のコピーライトは1732年に失われ、 1710年以後に発生した著作権は1739年以後順次失われると解釈される。一方、 1710年法が保護しているのは、この法律の成立以前から存在していたコモン・ロー・ コピーライトであると考えるならば、 コピーライト侵害に罰則を与えるという制裁の効力について時間的制限が規定されて いるのであると解釈することも可能だった。 議会側の目的は前者の解釈だったが、書籍業者側にしてみれば、 コピーライトが彼らの財産として 150年にわたって継続してきた事実があった。 そうであるならば、それはすでにコモン・ ロー上の権利だと主張することも無理ではなかったのである。
16.2 国外海賊版1709年制定法は、イギリス(イングランドとウェールズ) に適用される国内法だったから、 イギリスの出版物がアイルランドやスコットランドで海賊出版されても処罰すること ができなかった。(6条の規定は、 スコットランドの業者がイギリス国内において 1709年制定法の規定に反した場合に、 損害賠償請求訴訟をスコットランドの裁判所で行うことを規定しているのみ)ただ、 そうした海賊版が販売目的でイギリスに輸入されたとき、 初めてそれは処罰の対象になったのである。また、 権利者が侵害を排除し損害を賠償させるためには、侵害行為が行われた後に、 差止請求をしたり金銭債務訴訟を提起するしかなかった。したがって、 イギリスの辺境地域にさまざまな経路から侵入して来る海賊版を逐一訴追することは ほとんど不可能だった。
17 書籍業界の変化
17.1 著作者たちの試み1709年制定法が与えた進歩的影響は、著作者の方に顕著だった。 少なくとも趣意文の冒頭に著作者が権利の源泉として謳われたことは、 彼らの権利者意識を向上させたのである。1715年以降、著作者自身の費用による出版が一時的に増加する。これは、 自らの作品による利益をなんとか自らのものにしようとする著作者たちの努力の現れ だとみることができる。1710─1773年の間に、160人の書籍業者以外の人物が、 印刷業者に印刷を依頼して315冊の書籍を出版している [30]。 当時の書籍販売業界の主な取扱品目は、依然としてシェイクスピアやミルトンなどの、 安定した人気を維持している、すでに古典化した作品であり、 全く新しい出版物が刊行されることはそれほど多くなかった。 その中で315種類の新しい出版物が、書籍業者以外の人物から出版されていることは、 決して少ない数ではない。 こうした出版は、18世紀の終わりまでには衰退してしまう。その原因には、 複雑な出版業界の流通経路を十分に活用できず、 経営的に成功しなかったという理由もある。しかしそれ以上に、書籍業者たちが、 こうした個人出版書籍を積極的に宣伝しなかったのも大きな理由である [31]。書籍業者たちは、 出版事業に際して、わずかでもコピーライトの持分を持っており、 積極的に宣伝し販売量を増やすことで、 取り扱いから生じる利益の他にコピーライト持分に応じた配当金を期待することがで きた。ところが、 このような個人出版からは配当金の利益が期待できないのであるから、 煩わしい宣伝などするはずがなかったのである。 また、個人出版において経営的危険を避けるために、「注文出版」 (retail subscription) と呼ばれる形態が生じた。 すでに印刷されている書籍の版について、書籍販売業者たちの間で注文者を募り、 未製本の印刷シートの状態で売却したのに始まり、最終的には、 印刷するしないが決定される以前に、 書籍のコピーライトの持分への加入者を募集することになった。 これらの二つの方法は出版者たちにの間では、「卸売」(wholeseling)、 「コピーライト加入」(copyright subscription) と呼ばれた [32]。しかし、 この注文出版形態も18世紀の終わりには衰退してしまった。その理由は、 注文者から前金を受け取ったものの出版されないなどのトラブルが多かったからであ る [33]。また、 個人出版と同様に書籍販売業者たちが積極的に宣伝をしなかったことも原因として挙 げられる。 このように個人出版はなかなか困難であり、 著作者たちは結果的に書籍販売業者に従属しなければならなかった。 首尾よく第1版の売行が好調であれば、 書籍業者たちからコピーライトの譲渡を打診された。 面倒ごとを嫌った著作者は喜んでコピーライトを売却してしまった。 第1版が著者から出版されていても、第2版以降が、 書籍業者から出版されている例がしばしば見られるのである [34]。
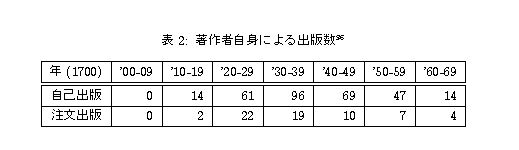
17.2 学術振興協会また、コンガーたちが握った流通経路の独占から生じる権力が、 一つの試みを排除した例として、学術振興協会があげられる。1735年に「学術振興協会」(Society for the Encouragement of Learning) と呼ばれる、小冊子出版業者たちが結集した出版協会が設立された。この協会は、 コンガーたちの同業者集団が保有していたものとは別のコピーライト系統の集団だっ た。この協会は、資本金を募り、事務所を設け、専属の事務員をおき、 著作者個人に直接に出版の便宜を与え、 出版から上がる収益をその費用を除いて著作者に直接与えようとする目的によって設 立された。学術振興協会からは優れた出版物がいくつか刊行され、 それらの出版事業が企画として失敗していたわけではなかった。しかし、彼らは、 書籍流通の部分で大手の書籍販売業者の流通経路を利用するという失敗を犯した。 協会の想定した流通におけるそれぞれの業者の取り分の設定が、 複雑な慣行によって作られていた既存の書籍流通機構とうまく調和しなかったために、 学術振興協会の出版物は書籍販売業者たちの十分な販売促進を受けることがなく、 経営的に破綻してしまったのである。 そして学術振興協会は1749年には解散してしまうのである [35]。
17.3 新しい独占者たち書籍業界のたどってきた決して平坦ではなかった過去と、 やがて到来する1740年以降の「書籍業者たちの戦争」(Battle of Booksellers) と呼ばれるようなコピーライトをめぐる法廷内外での紛争のことを考えれば、 1709年制定法の保護が全ての出版物に及んでいた 1710年から1730年までの書籍業界 は、きわめて平穏だったと言っても言い過ぎではない。出版取引におけるこの平穏さの理由は、 1709年制定法が十分な効力を発揮して書籍取引秩序維持に貢献したからではなかった。 むしろ、1710年から1730年の期間に拡大した市場を背景に、 大手の書籍業者たちが最も大規模な独占を成功させていたことがその理由なのである。 このため、制定法によって海賊版が禁止されているという一点を除いて、 1709年制定法は忘れ去られてしまっていた。その証拠に、 コピーライトの独占者たちは自分たちのコピーライト取引に部外者が参入することを 嫌い、 1709年制定法で義務づけられていたコピーライト登記さえ行っていなかったのである [36]。 また、海賊版の抑えこみに成功したのも、制定法の条文によるというよりも、 独占が作りだす権力のおかげだった。 建前ではコピーライトは自由に売買されることになっていたが、 実際には少数の人間にしかコピーライトの売却は知らされず、相変わらず「競り」 による独占が維持され続けていた [37]。このような理由で、 「コピーライトの史的展開(4)」 で述べたような書籍仲買業者たちによって構成されるコンガーは、 純粋なコピーライト保有者たちのコンガーによって取って代わられたものの [38]、 コンガーの業界に対する影響力はますます大きくなり、 海賊版を取り扱う小売業者に圧力をかけて海賊版を流通網から排除するという手法を 相変わらず使うことができた。 1709年制定法の語句など法廷でしか用がないものだったし、 法廷に持ちこむ前に海賊業者を破産させるくらい簡単だったわけである。
18 1709年から 「書籍業者の戦争」以前までの裁判記録 次に、1709年制定法が実際にどのように運用されたのかを検討するために、 1709年制定法が制定されてから「書籍業者の戦争」以前までの裁判記録を概観する。 1712年に大法官府において書籍業カンパニー 対 パートリッジ (The Company of Stationers v. Partridge)事件 [39]が記録されているものの、 この事件は1709年制定法の効果をめぐって争われたわけではなく、 暦の出版勅許をめぐっての事件だった。ここでは、 国王が祈祷書の出版権を国王大権に基づいて保有することが確認された。 暫定的差止命令が発給されたようであるが、 大法官は差止命令の根拠となる権利について何らの言及もしなかったようである [40]。 1720年代から、 国王大権に基づかない通常の出版物について海賊行為の差止を求める大法官府の提訴 が見られるようになる。記録に残っている大法官府における事件として、
ところが、ナプロック事件で、大法官マクレスフィールド(Macclesfield)卿は、 被告がプリドー(Prideaux)という人物の『教会委員への説示』 (Directions to Churchwardens) という書籍を出版することに対して、 本案的差止命令(perpetual injunction)を発給してしまった [42]。 本案的差止命令の発給のためには、本案となっている権利について事実審理が行われ、 保護される権利が確定していることが必要とされる。 ナプロック事件で本案的差止命令が発給されたことは、 1709年制定法の保護期間が満了した後も、差止命令が継続することが暗示されており、 後にコモン・ ロー上のコピーライトが認められていた根拠の一つとして援用されることになるので ある。また、トンソン事件でも、マクレスフィールド卿は、争われている 『気のある恋人たち』(Conscious Lovers)が、 1709年制定法の保護の要件になっている書籍業カンパニーへの登記がなされていない のにもかかわらず、差止命令を発給してしまった [43]。 これらのことから明らかになるのは、大法官府は少なくとも、 差止命令の発給に関して1709年制定法を厳密に適用する必要性を感じていなかったこ とである。差止命令自体は、大法官府の裁量に基づくのであり、 必ずしも1709年制定法に依拠しなければならないものではなかった。しかし、 1709年制定法の権利の内容について、 裁判所の判断が不明確なまま1730年代を迎えることで、 コピーライト概念に混乱をもちこむことになってしまった。 また、暫定的差止命令については、本来ならばそののち訴訟を継続して、コモン・ ロー裁判所で権利について確定されるべきだったのである。しかし、 出版業者たちは差止命令が発給されると満足してしまい、 その後の訴訟を継続しなかった。訴訟に多額の費用が必要だったこともあるだろう。 しかし、本質的な理由は出版業界の経営形態に起因すると思われる。出版事業では、 いかに速やかに在庫本を売却して投資を回収するかが最も重要な問題であり、 差止命令が発給されて被告側が印刷物を出荷できなくなった段階で、 被告側には回復困難な損失が生じるのであり、 それ以上の訴訟を継続する力は残らなかったのである。したがって、 差止命令の発給以上の法律判断は出版業者にとっては必要ではなかったのである [44]。 しかし、1709年制定法の保護期間が満了しはじめる1730年代にはいると、 しだいに判断に困難が生じるようになる。というのは、 1709年制定法の保護が満了した後、コピーライトも同時に消滅するのか、 あるいは付加的保護のみが失われるのかについて 1709年制定法は何らの規定もおい ていなかったからである。 1735年6月9日イヤー 対 ウォーカー(Eyre v. Walker)事件 [45] では1657年に第1版が出版された『人としての全ての義務について』 (Whole Duty of Man)の出版が争われた。この法廷で、ジェキル(Jekyll)記録長官 (Master of the Rolls) はウォーカーがその書籍を出版することを差し止めてしまった。 『人としての全ての義務について』に対する1709年制定法の保護期間は満了しており、 いかなる法的根拠に基づいてこの差止命令が発給されたのかが問題とされるようにな るのである。 このような法的根拠が曖昧な差止命令が1735年から1740年の間に連続して発給される のである。
これらの差止命令はほとんどが暫定的差止命令(injunction till hearing) であり、 いずれもが差止命令が発給された後、訴訟中止(acquiesced under) となっており、 確定的なものではなかった。また、 明らかに保護期間が満了しているものについても差止命令が発給された理由として、 1709年制定法の保護期間を延長するための法案が議会で審議中だったことも大きく影 響していると思われる。差止命令は予防目的でも発給可能だったから、 議会の制定法で保護期間が延長される可能性があれば、 それに基づいて発給することは差止命令の法理に反していない。 以上の事件は、すでに出版されていた書籍についての事件だったが、 未出版の作品の出版差止を求める事件も審理されていた。 1709年制定法の保護規定は書籍業カンパニーの登記簿に登記された書籍、 すなわち出版された書籍について適用されたので、 未出版の作品には1709年制定法は適用されなかったのである。しかし、 それらの事件についてもやはり差止命令は発給され続けていたのであり、 これがコピーライトが1709年制定法で与えられたのではなく、 制定法の規定に先行してコモン・ロー・ コピーライトが存在することを裁判所が認めていた根拠として主張されることになる。
これらの記録から、未出版の作品について公表権が著作者に存在していることを、 大法官府が認めてきたことがわかる。このことに関しては、 後の裁判でもほぼ論争なく承認されたようであり、コモン・ロー・ コピーライトの根拠として援用されることになる。ただし、以上の事件 (クィーンズベリー公 対 シェバー事件を除く)については、 他の訴訟記録の中の弁論で断片的に引用されているものであり、 その詳細は明らかでない。 1740年3月6日のギルス 対 ウィルコックス(Gyles v. Wilcox)事件 [61] という裁判記録から、 やや詳細な記録が報告されている。この事件はホール卿(Sir Matthew Hole) が執筆した『刑事訴訟の歴史』(The History of the Pleas of the Crown) と呼ばれる書籍の要約本(abridgement)の出版を差し止めることを求めるもので、 主として、その要約本が単なる語句の短縮にとどまるものか、 あるいは独立の著作物として認められる正当なものかが吟味されている。 両者の類似点についての判断は事実問題であるので、 この点について書籍業カンパニーの幹部が判断することになった。 最終的に仲裁が行われ、要約本は出版されることになったようである [62]。
19 小括 以上の検討から、1709年制定法の実態は次のように整理することができる。 1709年制定法の目的は(1)書籍業界の取引秩序の維持(2) 独占の排除(3) 著作者の保護であり、(3)の目的に着目するならば、 これは世界最初の近代的成文著作権法といえる。しかし、 実際には1620年代から徐々に形成された商慣習を制定法にまとめ、 かつ書籍業界のコピーライト独占を排除することが主たる目的であり、 むしろ産業統制法というべきものである。この制定法が実際に発揮した効果は、 1731年までイギリスの全ての書物の無断複製が禁止されているという一点であると言 っても過言ではなく、 この制定法を背景にしたロンドンの大手出版業者の市場支配力が取引秩序を安定させ ていたのである。 訴訟の場面においても事態は同様だった。 制定法によって全面的に無断複製が禁止されていたためか、 衡平法裁判所である大法官府は保護されている権利の本質について検討するまでもな く、無断複製を行う業者に対して暫定的差止命令を発給し続けた。 書籍業者たちは出版の差止さえ獲得すれば、 海賊出版業者に大きな経済的損害を与えることができたため、コモン・ ロー裁判所に訴え出てコピーライトの本質について議論する面倒を嫌った。 こうした結果、 制定法によって保護されている権利がどのような性質のものであるかが、 曖昧になってしまったのである。 このように不安定な状態に置かれていたコピーライトは、 二つの方向から問題をなげかけられることになる。第一は、 ロンドンの書籍業カンパニーの支配力の及ばなかったアイルランド・ スコットランドの書籍業者のイングランド進出であり、第二は1732年以降、 徐々に1709年制定法の保護が満了した作品が現れ始めたことである。 こうして1750年代以降、コピーライトをめぐる紛争は「書籍業者の戦争」 と呼ばれるほど加熱し、 この混乱のなかでコピーライトとはいかなる権利であるのかがようやく問いなおされ るのである。(つづく) Note
|


|
白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授 (Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences) 法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450) e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp |